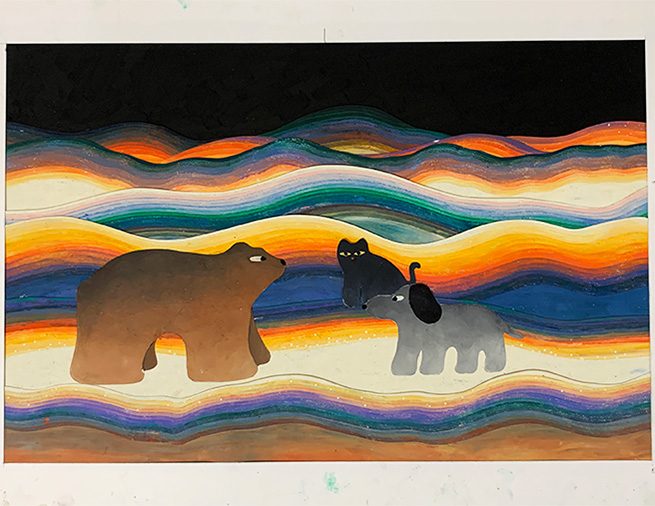こんにちは。編集部の早坂です。今回は、私が編集を担当した『ある晴れた夏の朝』(小手鞠るい 著/タムラフキコ イラスト)の原稿を依頼するにあたって、そのモチーフとなった人物と映画についてお話しします。
原爆の是非を討論の形で描いたYA作品
『ある晴れた夏の朝』は、アメリカ人をパートナーにもつ、アメリカ在住の日本人作家、小手鞠るいさんの作品です。さまざまな人種のアメリカの高校生8人が、広島・長崎に落とされた原子爆弾の是非を、肯定派、否定派に分かれて討論します。
小手鞠さんとの前作『きみの声を聞かせて』は、日本の少女とアメリカの少年が、ソーシャルメディアを通じて交流するというストーリーでした。次回作の原稿を依頼するにあたって、引き続きアメリカ在住という執筆環境を生かしつつも、今度は、若い読者の問題意識を刺激するような、骨太の作品を書いてもらいたいと思いました。
そのモチーフとなったのは、1人のアメリカ人を描いたドキュメンタリーと、1本のクラシック映画です。
討論のテーマは、1人の従軍カメラマンから
ジョー・オダネルは、原爆投下直後の広島、長崎を、自らのカメラを使って撮影したアメリカの従軍カメラマンです。なかでも有名な「焼き場に立つ少年」は、原爆が投下された直後の長崎で、亡骸となった幼い妹をおぶった少年が、火葬にするため順番を待つ姿を撮った作品。近年、ローマ法王がこの写真をカードにして、平和を唱えたことでも知られています。
ジョー・オダネルは帰国後、「広島、長崎の悲劇をくり返してはならない」と自ら写真展を開きます。原爆正当論が根強いアメリカ国内での批判に耐え、2007年、8月9日に85歳で亡くなるまで、各地で写真展を開催し、戦争反対、核兵器廃絶を訴えました。
この人物のことを日本の若者にも広く知ってもらいたいと思いました。と、同時に、アメリカ人の多くは、原爆投下を正当なことだと考えており、世代によっては、学校の教科書でそのことを学んでいるということも。
ただ、ジョー・オダネルをストレートに描くと、1人のアメリカ人の伝記となってしまうイメージもありました。小手鞠さんに書いていただくのならば、彼の考えや行動を、過去のできごととして見るのではなく、いまを生きている若者の問題意識としてとらえられるような作品にしてほしかったのです。
そんなとき、1本の古い映画を思い出しました。
討論を描くヒントとなった映画
父親を刺殺して殺人罪に問われているスラム街の少年は有罪か、無罪か。
映画『十二人の怒れる男』は、12人の陪審員による審議の様子を描いた密室劇です。最初の投票では、12人の陪審員のうち、11人は有罪。1人、陪審員8番(ヘンリー・フォンダ)だけが、無罪に投票。有罪になれば死刑となる少年のために、陪審員8番は、さらに話し合おうと提案します。そして審議は進み、多数決をおこなうごとに、無罪に投票する陪審員がひとり、またひとりとふえていきます。
陪審員室という密室で、事件の真相を追求していく緊張感の中、12人それぞれのキャラクターが見事に描かれた作品です。
「ヘンリー・フォンダが演じた陪審員8番=ジョー・オダネル」というストーリーを思いつきました。いまの学校現場では、国際力、コミュニケーション力を伸ばそうという教育が、いろいろと実践されています。登場人物をアメリカの若者たちにして、ディベートのような討論をやらせる形で物語をすすめてはどうか。そんなことが頭にうかびました。
ちょうどそのころ、小手鞠さんは『アップルソング』『星ちりばめたる旗』など、近代史、現代史を題材にとった作品で実績を重ねており、『ある晴れた夏の朝』の原稿依頼は、とてもタイミングが良かったといえます。
当初は、登場人物8人の高校生の中に、たとえば日本からの留学生などを入れる設定も検討しましたが、結果的には、ルーツの異なる日系人を2人にして、登場人物全員をアメリカ人にしました。日本に住む私たちにはわかりにくいのですが、彼ら2人も、「ごく普通のアメリカ人の意識」で生活をおくっています。そんなことも、この作品で示せたと思います。
編集者からの材料を、作家が「建造した」作品
『十二人の怒れる男』を小手鞠さんは見ていません。
実際にこの映画を見てしまったら、想像力がしばられ、なんらかの影響を受けて、うまく書けなかっただろうともいっています。よくよく考えると、この映画の場合は、「無罪=正」、「有罪=誤」という設定をもとに作られていますが、「原爆の是非」を、これと同じ俎上に載せるのは、土台無理があったように思います。
そのような意味で『ある晴れた夏の朝』は、こちらから提案した材料を、作家が見事に「建造してくれた」作品です。日本で35年、その後アメリカで30年、暮らしてきた小手鞠さんだからこそ、書くことができた作品といえるでしょう。
今月、この作品の英文版が刊行されました。国境を越えて、1人でも多くの人に読んでもらいたいと思います。
(編集部・早坂)