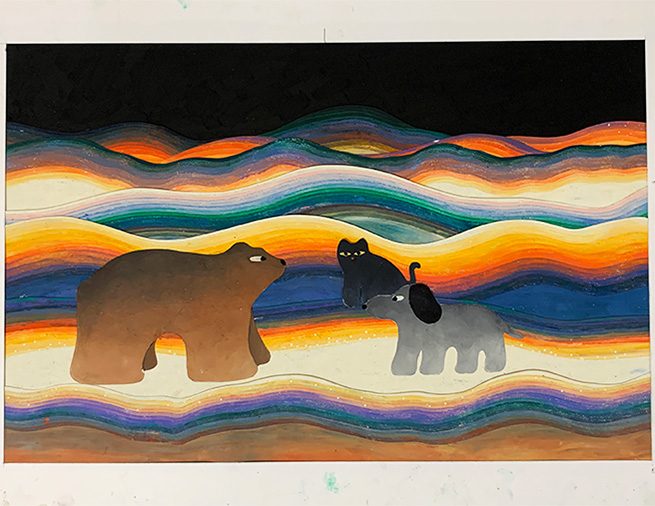『鈴をふる少女』
1973年(昭和48年)刊行
宮 敏彦/著 藤島生子/絵
偕成社は、今年創業82周年。このあいだに、数多くの本が刊行されてきた。
そのなかには、時代を反映しながらも、いまとなっては、すでに忘却のかなたとなった出版物も数多くある。ここでは、そんな過去の作品から、「知られざる一品」を紹介していこう。
今回取り上げるのは、1970年に刊行がはじまった「少女小説」というシリーズである。
『人生の目ざめと、あこがれを描く少女小説選集』 とあるように、十代の女子を読者ターゲットにしている。各巻のタイトルを見てみよう。
『愛と悲しみの季節』『心に愛の鐘がなる』『涙よさようなら』。
いわゆる青春もの、恋愛もの、といってよい。こんな書名も、その当時を感じさせる。
『アコひとりパリへ』『あなたも果実』『先生、まって!』。
さて、このシリーズのなかに、異彩を放っている書名があった。
『鈴をふる少女』
表紙を見ると、たしかに少女が鈴をふっている。

ほかの作品とはなじまない、なにか怪しげな雰囲気、少女の謎めいたほほえみ。いったいどのような話なのか。
母子家庭の敬子という少女が、ひき逃げに遭うところから、この物語ははじまる。あえなく敬子は帰らぬ人となるが、彼女は死ぬ間際、母親にこうつぶやいたのだ。
「かん、じ、き。かん、じき・・・」
「かんじき」とは、雪の上を歩くときにつける、あの装具にちがいない。ひき逃げ捜査本部の小野田主任と三峯刑事は、推理をめぐらす。
「島田敬子さんは、ひき逃げ車の特徴をわれわれに教えようとしたんだよ」
「犯人が、かんじきをはいていたとでもいうんですか、主任」
「ばかいっちゃいかんよ。東京で、この真夏にかんじきをはいて運転するなんて」
二人のかけあいもむなしく、犯人像はしぼれない。
だが、手がかりはあった。犯人は現場にライターを落としていたのである。刻まれたイニシャルはG・H。
その2年後、敬子の母親は、映画館で見た映像に衝撃をうける。本編上映の前に流されるニュースのなかで、ルームミラーに「かんじき」のマスコットをつけた車が映し出されたのだ。
「産業省の汚職、政界へ波及」ナレーションはつづく。
「汚職の波紋はついに政界へおよび、民政党の黒幕といわれる本堂次作氏が、24日午後、任意出頭のかたちで検察庁へ――」
松本清張を思わせる導入部、これは本当に少女小説なのか。そして、物語は中間部から「旅情ミステリー」へとおもむきを変えていく。
政治家、本堂次作の娘蘭子の溺死体が、旅行先の隠岐の島で発見される。彼女はみやげ物店で買った鈴を手にしていた。律令の時代、駅鈴とよばれる鈴が役人の身分証として使われていて、隠岐はその駅鈴が現存する唯一の土地といわれている。
この鈴は、なにか関係があるのか。
時を同じくして、こんどは本堂次作本人が、東京の自宅で不審な死を遂げる。検死の結果、青酸カリによる中毒死であった。隠岐と東京、この距離で単独犯はありえない。捜査本部は、本堂次作の「自殺説」にかたむくのだが……。
そこには、おどろくべき事実がかくされていたのである。
著者の宮敏彦氏は、少年鑑別所教官から作家に転身した経歴の持ち主で、当時、非行などをテーマに作品を執筆していた。中高年男性の読者(わたしです)までも、一気に読ませるプロット。
当時の少女小説は、恋愛ものばかりではなかったのだ。
(編集部 早坂)