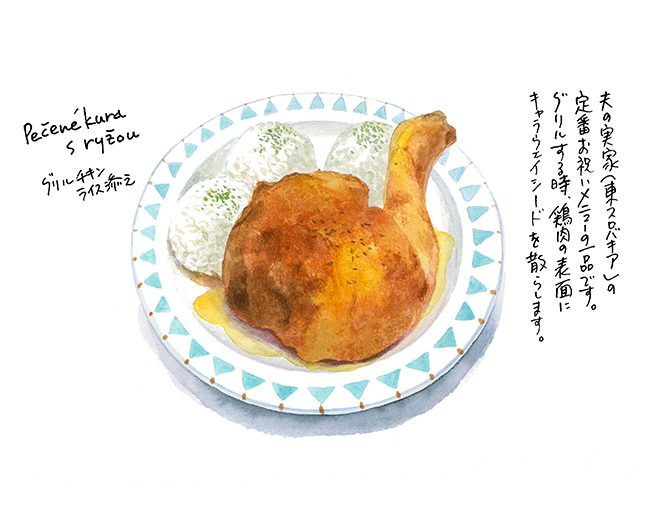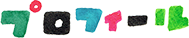「ドブルーフッチ!」とは、スロバキア語の「めしあがれ!」です。直訳すると「良い味を!」という感じ。つくった人や食卓に同席する人が、食べはじめる人に向かってかける言葉です。
このエッセイでは、中央ヨーロッパの一国、スロバキア共和国に暮らす降矢ななが、思い出や経験をからめながらスロバキアのおいしいものをご紹介します。
さぁ、みなさま、ドブルーフッチ!

留学をはじめて2年間、私はドナウ河沿い(*)に建つ寮で暮らしました。廊下のドアをあけるとベットと勉強机のある3人部屋が2つ並んでいて、シャワー&トイレの洗面所と、小さなキッチンがついていました。キッチンには小さい冷蔵庫が1台と、電熱コンロが1個置いてあります。ここで自炊ができる、と私はさっそく小さめの鍋とフライパン、コップとお皿2枚を買いました。お箸とペティナイフは、日本で愛用していたものを持ってきていました。
ブラチスラヴァで暮らし始め、不自由・不便なことは山ほどありましたが、その中の1つが肉を買うことでした。’90年代のはじめ、ブラチスラヴァには、スーパーマーケットのようにお客がカゴを手にし、品物を直接手に取って選べるお店はほとんどありませんでした。日本のケーキ屋のように、店員に頼んで、ケースや棚にある品物を取ってもらわなければ買いものはできません。石けんひとつでも、手に取って香りをかいで選びたいのが資本主義に慣らされた消費者のサガです。数年前まで社会主義だったスロバキアの店員は、客にサービスして売り上げをのばそうなんてこれっぽっちも考えていないので(当時)、取ってもらうときから、とてもめんどうくさそうです。それを返そうものなら、露骨にイヤな顔をし、不機嫌になります。でもそんなことでめげていてはスロバキアでは買いものはできません(当時)。けれど言葉が不自由でも指でさし示し、数の分だけ指を立てれば何となる買いものは、まだよいのです。
肉屋は、のぞいただけでひるんでしまいます。ガラスケースの中には、肉が3㎏、4㎏単位の塊でドン、ドン、ドンと並んでいます。鶏肉も丸ごと1羽が当たり前。お客が店員に「肉の種類と部分の名前、希望の重さ」を伝えると、その場で大きな包丁で切って、紙に包んで渡してくれるのです。ハムは薄切りにと頼むとスライスしてくれ、ひき肉も、頼むとその場でミンチにしてくれます。ブタの肩ロース薄切り350gのパックなんて売っていません。私は、お店のすみで、店員が肉を持ち上げダイナミックに切り分けているようすを眺めるばかり。

そんな私を助けてくれたのが、クロバーサでした。肉屋に入ると店員のうしろの壁にずらりと吊り下がっているのがクロバーサです。豚の粗びき肉にパプリカをメインにした香辛料で味つけされ、燻製された腸詰。スロバキアのチョリソーみたいなものです。これなら、日持ちがしそうですし、指差しショッピングが可能です。
紙に包んでもらった買ったばかりのクロバーサを、私は寮に持ち帰り、さっそく輪切りにして焼きました。電気コンロの上のフライパンの中で、それはチリチリと音をたて、切り口からオレンジ色の油がしみ出してきました。焼けたクロバーサをお皿に盛り、市場で買ったすっぱい千切りキャベツの漬物をそえると、自分の机に移動して、パンといっしょに食べました。焼いたクロバーサを噛みしめると、口の中に塩とパプリカ味の熱い肉汁と油がしみ出します。すっぱいキャベツがとてもよく合います。
これが私の留学中の記念すべき初自炊料理。まだルームメイトの誰もいない一人ぼっちの部屋の窓からは、学生たちが行き交う寮の中庭が見えました。
(※)ヨハン・シュトラウスのワルツ「美しき青きドナウ」で有名なドナウ河は、ブラチスラヴァ市内にも流れています。