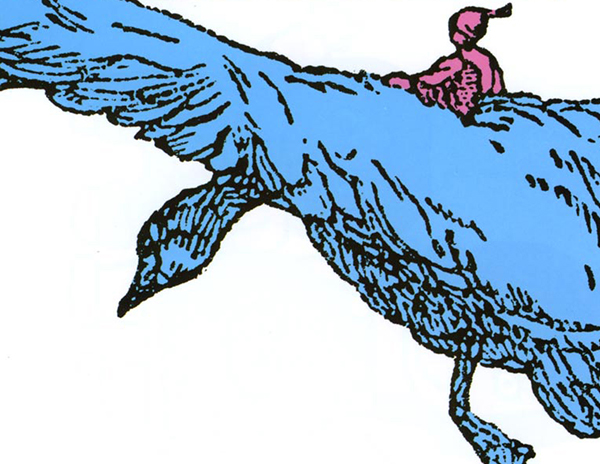「戦争もの」の物語はどれも凄絶に違いありませんが、この1冊の凄絶さは、明らかに他とは一線を画していました!
『流れる星は生きている』の語り手は、著者である藤原ていさん。(先日、たまたまこの本を読んでいる間に亡くなられました。98歳だったとのことです)戦争が終わった時に満州にいた藤原ていさんと家族は、それまでの暮らしを捨て、一途日本を目指して引き揚げてきました。いわゆる「満州引き揚げ」を描いたノンフィクション作品です。
中国の内陸地で突然「敗戦国民」となり、荷物も満足に持てぬまま汽車に飛び乗り、ぎゅうぎゅう詰めで何日も運ばれ、汽車を降ろされてからは交通手段もなく、足で歩いて日本を目指す……。
ううむ、こうして短く説明すると、「そりゃそんなの凄絶に決まってる」なのですが、この境遇はもちろんのこと、その道中に起こる数え切れないほどの出来事が、ひとつひとつ凄絶なのです。(ううむ、これも「そりゃそうでしょう」ですが……)
藤原さんは仕事があるからと引き揚げを遅らせた旦那さんと離れ、幼い子どもを3人も連れて引き揚げます。まわりには色々な日本人がおり、ご近所同士で組合を作って助け合いながら毎日歩を進めます。
しかし助け合うといっても、どうしてもそれぞれの身内は他人より大切にしたいし、財産も自分の分は持っておきたい。夜の間に仲間内でスリが横行したため、人目を忍んで草履に編み込んでまでお札を守るなど、人間の泥臭さがそこここに描かれます。これがまず凄絶①。
凄絶②は母親としてのていさんの様子です。5歳と3歳の男の子を両手に連れ、まだお乳を飲む赤ちゃんを抱えて引き揚げるていさん。母乳が出なくても、赤ちゃんにはなんとか大豆を煮た汁など代わりのものを飲ませ、芋をもっとと欲しがる2人の息子には、自分の分を分けてあげる。やっぱり母ってすごいものだ、と思います。
さらに、北緯38度線を目指し、歩いて山を越えるとき。靴もなくなり、裸足で山道を歩くので、ていさんも子どもも足の裏に色々なものが突き刺さり、化膿したまま延々と歩かなくてはいけません。それに子連れは他の人より時間がかかるので、列の最後尾。置いていかれたら道も分からなくなるのです。
そんな状況で、「もう歩きたくないー」とべそをかく息子を、ていさんはものすごい形相で怒鳴りつけます。「なにをぐずぐずしている!」「泣いたら置いていくぞ!」——そう、いつの間にかていさんは、男言葉を使うようになるのです。極限状態が続くとこんなにも人間は変わるのか……そしてそれでも、子どものことは、どんな形であっても生かそうとするのだな……、これが凄絶②でした。
ほかにも、旅の道中には、凄絶なことがいくつも待っています。といってもただ悲惨さが描かれるだけでなく、物語性があり、(こんなに過酷な環境であっても)登場人物の個性をていさんが細部まで捉えて描写しているというのが、この作品の魅力です。悲しく辛いテーマだけれど、読んで「おもしろかった……」と思える1冊でした。
最後に、この本のタイトルにもなった歌の歌詞をご紹介します。「なにか、わたしたちをひきつけてはなさない魅力をもっていた」という、仲間たちで口ずさんでいた歌だそうです。この物哀しい歌で、ていさんたちは、行き場のない不安や怒り、悲しみの気持ちを浄化していたのかもしれません。
わたしの胸に咲いている
あなたのうえたバラの花
ごらんなさいね 今晩も
ひとりで待ってるこの窓の
星にうつって咲いている
わたしの胸に泣いている
あなたのよんだあのお声
ごらんなさいね 今晩も
ふたりでちかったあの丘に
星はやさしくうたってる
わたしの胸に生きている
あなたのいった北の空
ごらんなさいね 今晩も
泣いて送ったあの空に
流れる星は生きている
(販売部 松野)