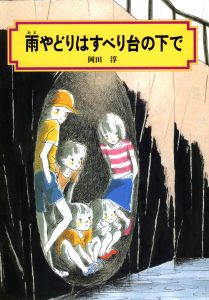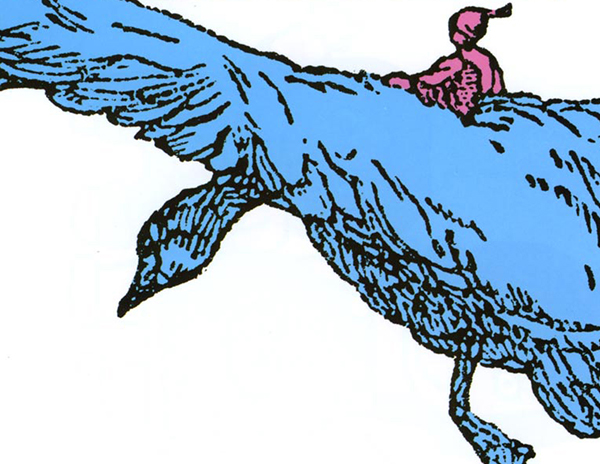これはこれは、なんて色気のある児童文学なのだろう…。色気というのは別に男女の恋バナだけじゃない。人と人とのつながりには多かれ少なかれ心と心の通い合う瞬間があり、それは大人だろうが子どもだろうがセクシーで、本作はそんな話の宝庫なのだ。
公園で遊ぶ10人の子どもたちを襲う突然の雨。今でも覚えているが、子どもの頃の雨宿りは大変な冒険で、とってもワクワクする出来事のひとつ。仲のいい友達同士ならなおさらだ。
そうやって大きなすべり台の下で、雨宿りしながらポツリ、ポツリと話し始めたのは、近くに住む謎の老人の事だ。みんなの口から出てくる話は、どれも不思議で、なぜか妙に暖かい。上質の短編映画のようなシーンが目の裏に浮かんでくる。そして不思議な事に、ひとりひとりが謎の人「雨森さん」にまつわるエピソードを話していくうち、ここにいる皆の事が、お互い今まで以上にちゃんと「見えて」くる。このあたりの展開が、息が詰まるほどロマンチックなのだ。そして物語は感動のラストへ進んでゆく。
ただひとつ、読み終わってからふと気になる事がある。この暖かい物語の中心人物「雨森さん」の謎の行動である。巻末の解説でも触れられているが、この摩訶不思議なエピソードの裏を返せば、もしかすると彼が味わってきたかも知れない悲しい過去が、音も無く見え隠れしてくるのだ。この本を何年もたって成長してから二度三度と読み返す人が多いのは、たぶんこのあたりの深さに理由があるのだろう。名作の名作たる所以を、読む人、読んだ年齢で違うものが見えてくる事であるとするならば、これは間違いなく名作中の名作。
岡田淳さん恐るべし! である。
(販売部 西川)