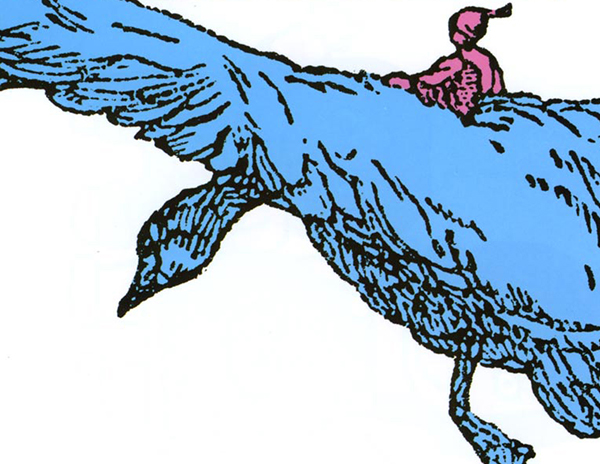海外ミステリーの場合、語感って大切ですよね。なにげなく文中にでてくる言葉、とりわけカタカナ語の響きが作品の雰囲気や世界観を盛り上げてくれて、日本からほとんど出たことのない、埼玉の奥の方でひっそりと暮らしている私なんかでもすぐさま海の向こうへと連れて行ってくれます。
今回はアガサ・クリスティの『大空の殺人』を例にしてみてみたいと思います。
まずは登場人物の名前。これ絶対大事ですね。事件の被害者はマダム・ジゼルという金貸しの老女でした。彼女の因業ぶりがストーリーの根っこを支えているのですが、それにしてもなんと悪そうな名前!濁点が多くて文字の見た目までザラザラしています。しかし、悪の中にもかすかな気品や矜持を匂わせる秀逸な名前です。
それから考古学者のデュポン親子。これもいい名前ですね。彼らはいつも先史時代の土器の話をしているちょっと変わった親子なのですが、このデュポンという名前が周囲との異質感をうまく表しています。しかもそれでいてどこか知性も感じさせるので、単なる奇天烈な印象とは違う。おまけに言うと、デュ「パ」ンじゃなくて、デュ「ポ」ンというのもちょうどいい。「パ」ンだと一気に貴族っぽくなってしまって台無しですよね。
人名のほかにも例えば、ジェーンやホーベリー伯爵夫人が訪れたル・ピネーの街。殺人が行われた飛行機が到着したクロイドン空港。 ポワロがジェーンとゲイルを連れて食事に出かけたお店はモンセニョールで、そこでポワロが注文したのはコンソメとチキンのショーフロワでした。(ちなみにこのシーン、まさかポワロにそんな考えがあったとは、全然気づかなかった!)
前出のデュポン親子の会話に出てくる先史時代に関するワード ― サマラとか、テル・ハラフとか、サクジェ・グーズとか ― も楽しいです。ちなみにクリスティの再婚相手は考古学者だったそうですね。
さて、語感の観点からもうひとつ触れておきたいのは、やはりなんといってもポワロのセリフについてです。ところどころにフランス語の発音がルビとして併記されます。なぜかというとポワロは普段英語を話しますが、時々フランス語が混ざるんですね。例えば、
「トレ・ビヤンけっこう」
「メ・ズウイそうですとも」
「エヴイダマンもちろんです」
「レ・ファム女性として」
「メ・ザンファン・エスカ・セ・ポスイーブルいやはやまったく、そんなことがありうるでしょうか」
「イル・フォー・コンティニユエ調査を続けなければ、、、」
「ア・ドウマンまたあした」
といった具合です。これらのセリフを読むときに、ちょっと立ち止まってフランス語独特の鼻にかかったような発音を脳内再生させてみると、おもむろに、ポワロのあのいかにももったいぶった感じ、得意げで慇懃で回りくどい紳士の姿が浮かんできませんか。(いや別にフランス語の知識がなくても大丈夫。大事なのは雰囲気ですから。タレントのタモリさんがやっていたフランス人モノマネと一緒ですね。)
初めて読むときはちょっと目障りかもしれませんが、でもすぐ慣れます。私も子供のころにこの本を読んだときは正直言って読み飛ばしていましたが、いまこの記事を書くために読み直してみると、いちいちこのルビが楽しい。
偕成社文庫の翻訳は完訳ですからこのあたりの表記もばっちり載せています。偕成社文庫、トレ・ビヤンけっこうです!ぜひ一度味わってみてください。
(総務部 河本)