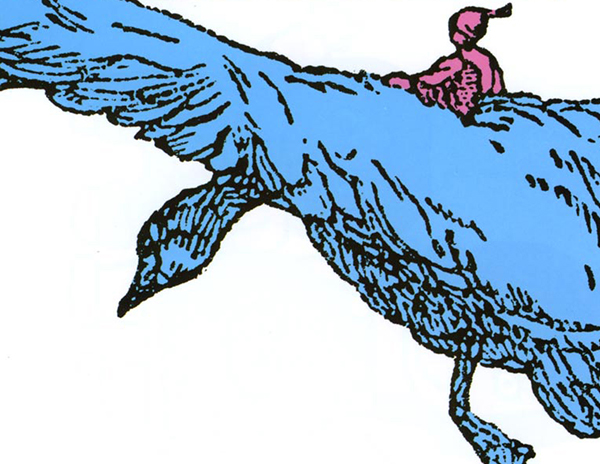舞台は19世紀末のドイツの小さな町。平凡な父親から生まれた、非凡な少年ハンスは、難関の神学校に入学するが、周囲の期待にこたえんとするばかり、その重圧にたえかね、ついにはひざを屈し、立ちあがる気力もなく、しだいに挫折と転落の一途をたどっていく。
生きていれば辛いこともあります。しかし少年はそれを乗りこえることができなかった。
作者のヘッセはこうつづります。
「なぜハンスはもっとも感じやすい危険な少年時代に、毎日夜なかまで勉強しなければならなかったのか。なぜ彼から飼いうさぎをとりあげたり、故意に友だちからとおざけたり、さかな釣りや散歩を禁止したり、空虚な卑俗な理想をつぎこんだりしたのか。なぜ当然やすめるはずの休暇を彼にあたえなかったのか。」(一部略)
つらい、胸につきささるような描写です。
ひざを地につけて屈している人を、ふたたび立って歩かせるものは、自分がこどもだったときの思い出であり、そのときに感じたあたたかさだと思います。
ハンスは、艱難に立ちむかう盾を持っていませんでした。そして起きあがるつえを手にしないままに、思春期をむかえてしまったのです。
ボク自身にもかつて、まいにち暗い穴をのぞきこんですごすような時期がありました。
そのとき、ひざに手をつきふたたびその身をすっくと立ちあがらせてくれたのは、幼少期から思春期にかけての、楽しかった思い出でした。
それは庭にわだちができるほどこぎまくった三輪車であり、祖母宅のそばにあった煮えくりかえるように熱い銭湯であり、水草のあいだできらめくハヤの横腹であり、「Death! Die!」とヘヴィ・メタルに首をふりながら叫んだ記憶でした。
だれに教えられたわけでもなく、そのときボクの気持ちは、自然と「たのしかったおもいで」へと向かっていったのでした。そしてそれが本当の意味でのいやしとなって、また前に進めるようになったのです。
こどものときに負った心の傷が、その人の一生を左右することがあるように、小さいころに楽しかった思い出をせっせと胸の奥にためることは、将来の自分を強く、楽観的にすることになります。
そしてそれは、そのこと自体「毎日が楽しい」ということのあかしにほかなりません。
『車輪の下』が教えてくれることがあるとすれば、そんなことです。
(編集部 ふ)