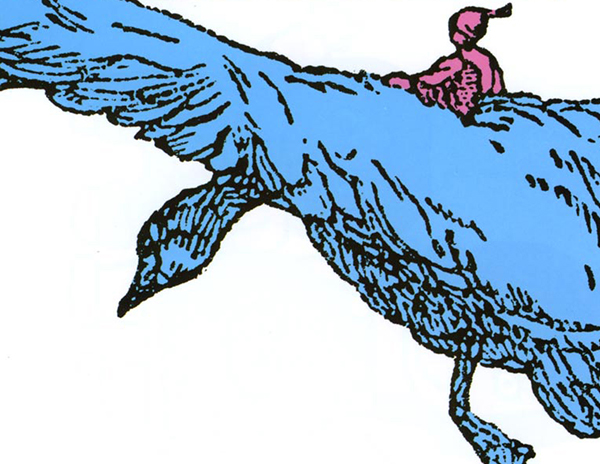主人公のヒルベルは母親から養育を放棄され、養護施設で暮らしています。どんな子なのかというと、「読み書きをならうためにじっとすわらされると、とたんに不安が頭をもたげるのだった。だから、いすの上でごそごそとしりを動かし、とつぜん立ちあがり、部屋じゅう走りまわって、たいくつだ、たいくつだ、といった。ヒルベルにはがまんするということが、どうしてもできなかった。(中略)~あまりにもたくさんの考えや、喜びや、おそれがつまりすぎているので、おとなのいう、いわゆる《きちんと勉強する》ことなどできっこなかった。」
けれども、ヒルベルは、施設での生活をなんとかやっていくことをおぼえ、いじめから身を守ることをおぼえ、しかられたりなぐられたりしないためのやり方を身につけていきます。
施設を脱走したときに出会った羊の群れをライオンだと思いこむ無邪気さ、自分へのぬれぎぬを晴らすためにとった用意周到な行動、大人からなぐられたときにとった行動などは、読んでいてにやりとさせられつつ、切なくなってしまいます。
こんな彼を気に入って目をかけてくれる施設の先生やお医者さんもいて、ヒルベルと関わろうとするのですが……。
作者のヘルトリングは、社会の現実を直視しながら、とても愛情深くヒルベルを描いています。
それは作者のあとがきにもよくあらわれていて、「ヒルベルは病気だったのか」という問いに対する答えのひとつとして、つぎのように書いています。
「医者ではなおせない病気だ。つまりね、ヒルベルには、ほんきで心配してくれる人がだれもいなかった。(中略)~この病気は、みんながそっぽをむいて、ヒルベルをかわいがる人がひとりもいなかったら、ぜったいなおらない病気だ。」
子どもにとって、無条件に根気よく気にかけてくれる大人がまわりにいることが最もだいじなのだ――というヘルトリングの強い思いが伝わってきます。
ヒルベルがその後、どこかでそんな人に出会っていることを願わずにはいられません。
この本には、心理学者の故河合隼雄氏が書かれた解説が別刷りではさみこまれていますので、そちらもぜひ。
(編集部 和田)
この記事に出てきた本
読み込めませんでした。