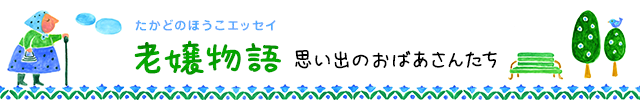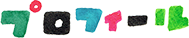1986年の1月。友人と私は、水色の空が輝くギリシャの片田舎、ペロポネソス半島のパトラス市郊外で、2週間余りを客人として過ごした。その半年前に知り合ったエレーニという画学生が、実家に招いてくれたのだ。––––と、こうさらりと書きはしたものの、〈ギリシャ〉や〈ペロポネソス半島〉などという遠い遠い、しかも(今だって新聞をさかんに騒がせているにもかかわらず、どうしても)古代の風を感じずにいられない地名の内部に、すっぽり入りこんでいたなんて、今では夢のようだ。
エレーニの家は新築(中)で、広大な敷地をほしいままに古家も解体せず、父親や男兄弟たちが手ずから石を積みあげ漆喰を塗るなどして(ほぼ)建て終えた家に移り住んでまもなくというところだったから、外も内も歴史の重みを感じさせるどころではなく、まだがらんとして殺風景だった。
けれど、どこまでも続いているような庭には、果実をいただくさまざまの樹木があちこちに立ち、孔雀が数羽、ふうわりと古家の屋根まで舞い上がってとまったり、光沢のある長い尾を地面にひきずって歩いていたりして、まるでビネッテ・シュレーダー(※)の絵本の一場面を見ているような気になるのだった。
時には、彫像そのもののようなエレーニの兄が、気味悪いほど引き締まった毛のない大型の猟犬を何頭も引き連れてその庭を抜け、狩猟に出かけていく。それは小説や映画で繰り返し出会っていながら、実際に目にすることのけっしてなかった、ヨーロッパの田園の光景そのものだった。
そんなカフカ邸を(あのカフカ以外にカフカがいるなんて思ってもみなかったけれど、ギリシャ人のエレーニの姓もカフカなのだった)いろんな人が訪れたが、みな表向きの理由のほかに、生きて動いている日本人というものを一目見ようという下心を抱いてやって来るのはまちがいなかった。
いちばん頻繁に現れたのは黒頭巾をかぶった全身黒ずくめの小さなおばあさんで(未亡人の典型的な服装なのだそうだ)エレーニの母親と話し込みながら、ちろちろっとこちらを伺う。むろんこちらだって観察される一方ではないから、おばあさんが帰ったあとは、その真似をして「ポッポー」と言い合って友人と笑った。「ポッポー」というのは相槌で、日本語なら「あんれまあ!」「おっとぉ…」「ひゃあ」といったところか。若い人はあまり言わないようだったから、おばあさん用語なのかもしれない。〈ポッポーばあさん〉は、話の合間に「ポッポー」「ポッポー」と口をつきだしては、目をパチクリさせたり眉をひそめたり、のけぞったりしながら、隙を見てちろっとこちらを伺うのだった。
でも思い出すたびに、心地よい微風を感じるのは、〈ポッポーばあさん〉とはまた別のおばあさんたちがいた、昼下がりの光景なのだ。
その日エレーニは、ぜひとも裏の家を訪問してあげてほしいといい、我々を連れ庭の木立をしばらく進み、垣根を通り抜け、白い小さな家の戸をくぐった。
入ってすぐの白壁の小部屋に、またしても黒頭巾をすっぽりかぶった黒ずくめのおばあさん姉妹が2人、歩くのが大儀そうに、テーブルの前にじっとすわっていた。生まれて一度も日本人を見たことのなかったおばあさんたちは、深い皺に埋もれた大きな目を光らせながら私たちをじいっと見つめて、にっこりした。エレーニがお茶を淹れてくれたあと、ちょっと用があるからここで待っててね、と言い置いて出ていってしまうと、もう私たちに通じる言葉はなかった。
4人はテーブルを囲んだまま、時たま目を合わせてはおたがいににっこりし、お茶をすすり、あとはただ黙って、高いところについた小ぶりの窓から、そろって外を見つめてだけいた。
開け放した窓からは、明るく澄んだ溌剌とした水色の空と、空を背景にした、レモンの木の梢が見えていた。まるで生きた額絵のようだった。あのたわわになった大きなレモンの黄と、かすかにそよぐ生い繁った葉の緑を、今もくっきりと思い描くことができる。
老いた姉妹は、お姉さんがマリア、妹はアフロディテというのだった。この小さな家にひっそりと、聖母マリアと美の女神アフロディテが同居していたなんて、「ポッポー」と言わずにいられようか。(愛と美を司るこのギリシャ神話の女神は、ローマ神話のウェヌス、いわゆるヴィーナスにあたるのですね)
白い部屋、黒い服、水色の空、黄色の果実、緑の葉……。そよ風と沈黙。
 ギリシャの片隅でやり過ごした、くっきりとした色彩の昼下がりのひとときが、今なお優しく美しく蘇るのは、そのたびに、マリアとアフロディテという祝福された古代の名前が、鈴の音のように記憶の中で鳴り響くからなのだ。
ギリシャの片隅でやり過ごした、くっきりとした色彩の昼下がりのひとときが、今なお優しく美しく蘇るのは、そのたびに、マリアとアフロディテという祝福された古代の名前が、鈴の音のように記憶の中で鳴り響くからなのだ。
※ビネッテ・シュレーダー
1939年、ドイツのハンブルグ生まれの絵本作家。『お友だちのほしかったルピナスさん』でBIB金のりんご賞を受賞。絵本作品は『わにくん』『ラ・タ・タ・タム』など多数ある。