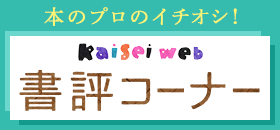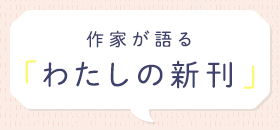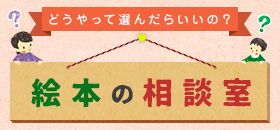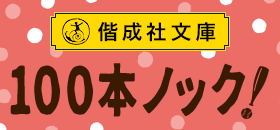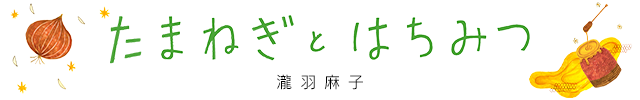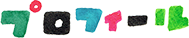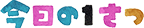大丈夫。わたしは、ひとりでも大丈夫。
ミルクが満足そうにうなずいた、ように見えた。そして、くるりと回れ右して、路地の奥へむかって歩きはじめた。やっぱり、追いかけっこがしたいらしい。
ブロック塀にはさまれた細い道は、歩きにくかった。
表の舗装された道路とちがい、砂地がむきだしで、でこぼこしている。おまけに、ところどころ水たまりもできている。歩きづらそうなそぶりもなく、すいすいと進んでいくミルクを、千春は足もとに注意しながら追いかける。
この道のことは、紗希も知らないはずだ。明日にでも教えてあげたら、びっくりするだろうか。
千春から紗希になにかを教えるなんて、ちょっと珍しい。
いつもは紗希のほうが、千春にあれこれ教えてくれる。幼稚園のときからそうだった。
尻ごみしている千春の手をひっぱってクラスメイトたちの輪に加わり、さかあがりの練習
に根気強くつきあい、学校の宿題でわからない問題があれば説明してくれた。紗希は運動
も勉強もよくできる。
「本当に、助かるわ」
お母さんはよく紗希のお母さんに言っている。
「うちの子はちょっとぼうっとしてるから。紗希ちゃんみたいにしっかりしたお友だちがいてくれて、よかった」
ぼうっとしてるわけじゃないんだけどな、と千春はひそかに思う。千春は千春なりに、考えてはいるのだ。ただ、考えめぐらせているうちに時間が過ぎて、口を開こうとしたときにはもう話が先に進んでしまっていることが、ときどきある。お母さんも紗希も、千春に比べてかなり早口だ。
小道のつきあたりは背の高いフェンスでさえぎられ、そのむこう側には、もくもくと木が茂っている。公園かなにかだろうか。遠目には行きどまりのように見えたけれど、フェンスに近づいてみると、左右に道が延びているのがわかった。
どっちに曲がるかな、と気を散らしたのが、よくなかった。
小石につまずき、千春はつんのめった。二、三歩、ふらふらと前へよろめく。水たまりの縁をかすり、正面のフェンスに両手をついて、なんとか転ばずにすんだ。ふう、と大きく息をつく。
そこで、膝のあたりがひんやりと冷たいのに気づいた。