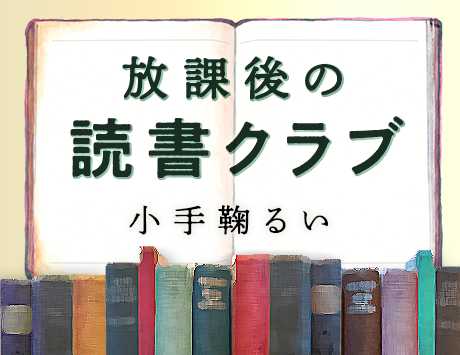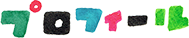「読むこと」をテーマに、自身の読書体験、おすすめの本などについて、作家・小手鞠るいさんが語ります。
子どものころに読んで、激しいショックを受け、夜も眠れなくなり、しかし、こわいもの見たさで何度も何度も読みかえしてしまい、読みかえすたびに、背中をぞくぞくさせていた、世にも恐ろしいお話。
井上靖の著した「補陀落渡海記」はわたしにとって、忘れえぬ「命の物語」である。
子どものころにはどんな本で読んだのか、記憶には残っていない。
大人になってから読んだのは『楼蘭』という短編集(新潮文庫版)の中に収められている一編だった。
もともとは単行本『洪水』の中に収録されていて、この本の刊行は昭和37年ということだから、わたしが6歳のときに発表された短編である。
もしかしたらわたしは、この単行本を町の図書館で借りて、読んだのかもしれない。学校の図書室には決して置かれていないような本を、当時のわたしは町の図書館で見つけては読んでいたから。
おそらく10代のときに初めて読んで以来、ふとしたときに思いだし、思いだすたびに読みかえしてきたから、かれこれ50年くらいのおつきあいになる。
このエッセイを書くために、ゆうべ、ふたたび読みかえしてみた。
前に読んだのはいつだったか、覚えていないものの、まあ、10年ぶりくらいだと言って間違いはないだろう。
やっぱりぞくぞくした。
「ぞくぞく」ということばを辞書で引くと(1)嬉しさに心が浮きたつさま。うきうき。(2)緊張や恐怖、嫌悪などで身のふるえをおぼえるさま。(3)寒さや病気などで悪寒の走るさま。と、解説されている。
子ども時代は明らかに(2)だったと思うし、その後も長きにわたって(2)だった。ただ、その度合いはうすまったり、深まったりしていたはずだ。緊張と恐怖と嫌悪の比率にも変化があったことだろう。
さて、ゆうべの「ぞくぞく」はと言えば、それはなんと(1)だったのである。
緊張、恐怖、嫌悪、もちろん悪寒も感じなかった。
そう、わたしの気持ちは喜びのあまり、浮きたった。うきうき、である。
ひとことで言うと、このお話は、ひとりのお坊さんが生きたまま海に放置され死に至る、という残酷きわまりない物語である。
お坊さんは小舟に乗せられ、座ったままの姿勢の上からすっぽり箱をかぶせられ、その箱は外れないようにしっかりと、舟底に打ちつけられている。狭い暗闇に閉じこめられた状態で、海に流されたお坊さんを待ちうけているのは、わずかな食料が尽きて餓死するか、海が荒れて溺死するか、あるいは、苦しみに耐えられず舌を噛みきって自死するか、いずれにしても安楽とは言えない死である。
そんなお話を読んで、うきうきするとは、いかがなものか。
主人公のお坊さん、金光坊の年齢は、61歳。
わたしよりも3つ、年下である。
まだ60代になったばかりという若さで、いったいなんのためなのか、だれのためなのか、自分の死が何かの役に立つのか、なんの役にも立たない無駄な死なのか、そもそも自分はなぜ死ななくてはならないのかもわからないまま、みずから死出の旅に向かう舟に乗りこまざるを得なかった彼の苦悩とは、死に対する恐怖とは、どれほどのものだったのだろう。
夏から秋にかけては恐ろしい程早く日が経った。金光坊は毎日のように今日は何日かと傍に居る者に訊ね、返事を聞く度にそんなことがあろうかと思った。金光坊は相変らず読経三昧に日を送っていた。立秋からあとは一日の時間が信じられぬ早さで飛んで行った。朝も晩も一緒にやって来るように思われた。
金光坊は、はっきり言って、依然として補陀落渡海する心用意が何もできていない自分を感じていた。読経の合間合間に、相変らず自分の知っている渡海者たちの顔は次々に立ち現れて来たが、現在の金光坊には、それらの顔は、それぞれに親しみも懐しさも感じはしたが、併し、例外なく補陀落渡海とは何の関係もない人間の顔に見えた。自分の渡海など考えてもいない長い間、金光坊が彼等に対して懐いていた崇高なものはすっかりその顔からは消えていた。
読みながら、わたしの心はうきうきしていた。
誤解を恐れず書けば、わたしは笑顔になっていた。
この冷徹な文章、この滑らかな筆の運び、この息をつく暇も与えないストーリー展開。行間に漂う静けさと激しさ。何もかもが素晴らしくて、わたしはこの素晴らしい作品を「読める喜び」に浸っていた。
最後はどうなるか、すでにわかっているのに、そこに至るまでのお坊さんの葛藤を何度でも文字で味わいたい。するめのように、噛んで、噛んで。
噛めば噛むほど、じわじわと滲みでてくるお坊さんの苦しみがわたしに、喜びを与えてくれる。
これこそが文学を読む喜びなのだとわたしは思う。
1回目はうまく死ねなくて、生きて島へたどり着き「助かった」と安堵し、つかのまの生の喜びを味わいながらも、ふたたび舟に乗せられることになった(これがまたなんとも言えず残酷です)金光坊が最後にどんなことばを発したのか、最後にどんな文章を書いたのか、それはみなさん自身の目で確かめてほしい。
作家は答えを用意している。
答えを書かないというやり方で。
金光坊は筆を擱くと、直ぐ眼を瞑った。清源は師の息が絶えたのではないかと思ったが、まだ脈もあり体温もあった。清源は師の筆跡からそれを書いた師の心境をはっきりと捉えることはできなかった。それは金光坊漸くにして到達することのできた悟りの境地のようでもあり、また反対に烈しい怒りと抗議に貫かれたそれのようでもあった。
間もなく急拵えの箱が金光坊の上にかぶせられ、こんどはしっかりとそれは船底に打ちつけられた。その仕事が終ると、まだ生きている金光坊を載せて、舟は再び何人かの手で潮の中に押し出された。
たったひとりの例外もなく経験することであるのに、たったひとりの例外もなく「それを正確に書く」ことができない。書くことができないからこそ、作家は死を書くことに魅入られ、夢中になるのではないだろうか。
わたしたち読者は、作家の書いた「死を読む」ことができる。
読むことで死を、ぎりぎりのところまで、擬似体験できる。
命の物語は生の物語であると同時に、死の物語でもある。希望イコール絶望。
金光坊はそのことを雄弁に語ってくれた。井上靖がわたしに語ってくれたのだ。