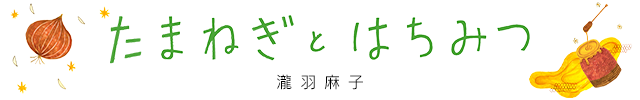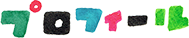それは、不思議な音だった。
立ちどまって、まわりを見まわしてみる。見慣れた通学路には誰もいない。歩道の右側にはブロック塀が延び、顔をのぞかせている桜の木から、ふわりふわりと花びらが舞い落ちてくる。左には車道をはさんで、二階建ての古ぼけたアパートが建っている。
ひよひよひよ、とどこかで鳥が鳴いている。似てるけどちがう、と千春は思う。さっき聞こえてきた音は、もう少し低くて、鋭くて、くっきりと澄んでいた。あんな音は、はじめて聞いた。はじめてなのに、どういうわけか、なつかしいような感じもした。
もう一度、耳をすます。
鳥のさえずりがやんだ。かわりに、なああ、とまたちがう声がした。見上げると、いつのまにか塀の上に白い猫が立っていた。赤い首輪をつけている。
「ミルク」
声をかけた千春には目もくれずに、ミルクはするりと歩道へ飛び降りた。そのまま堀に
沿ってまっすぐ走り、角でさっと右に曲がった。
取り残された千春は、のろのろと歩き出した。
ふだんのミルクはひとなつこい。ごろごろとのどを鳴らし、千春たちの脚に体をすりつ
けてくる。猫の大好きな紗希が、かわいいかわいいと全身をなでまわしても、逃げずにじっとしている。
紗希がいないから、がっかりしたのかもしれない。
今日は塾があるからいっしょに帰れない、と紗希は言ったのだった。正しくは、今日だけじゃない。これから毎週、月曜日と水曜日と金曜日はいっしょに帰れないらしい。
中学受験を専門とする進学塾に、紗希は去年の夏休みから通いはじめた。放課後にまで勉強するなんて大変そうだとはじめ千春は同情したけれど、塾生活は充実しているようだ。授業はおもしろく、ほかの学校の子とも知りあえて、楽しいという。
「ごめんね。千春、ひとりで大丈夫?」
「うん、大丈夫」
なるべく明るい声で、千春は答えた。
いつかこんな日が来るだろうな、とうすうす覚悟はしていた。本格的に忙しくなるのは六年生からかと思っていたから、五年生になってすぐというのは、ちょっと不意打ちだったけれども。
新刊トピック
連載
スタッフ記事
特集
終了した連載
-
朱川湊人
-
小手鞠るい
-
瀧羽麻子
-
小手鞠るい
-
村中李衣
-
竹田津 実
-
富安陽子
-
たかどのほうこ
-
岡田 淳
-
瀧羽麻子
1981年兵庫県生まれ。京都大学経済学部卒業。『うさぎパン』で第2回ダ・ヴィンチ文学賞大賞受賞。著書に『左京区七夕通東入ル』『左京区恋月橋渡ル』『左京区桃栗坂上ル』(小学館)『松ノ内家の居候』(中央公論新社)『いろは匂へど』(幻冬舎)『ぱりぱり』(実業之日本社)『サンティアゴの東 渋谷の西』(講談社)『ハローサヨコ、きみの技術に敬服するよ』(集英社)など。<br /> <br /> 写真撮影/浅野剛
この本を読んで、おねしょしても洗濯したらいいじゃない。おねしょはダメなことじゃない!と思えました。ぶたさんのおねしょがハートマークのところで、大笑いしていました!ノンタンにはいつも前向きな気持ちをたくさんもらえます。(3歳・お母さまより)