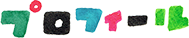「べつに信じなくっても、いいですよ~だ」
そう言いながら女の子は、人差し指のあいだについたままだったシールに、フッと息を吹きかけた。その瞬間、シールは空中に溶けたみたいに消えてしまう。
「すごい! 手品、うまいね」
「手品じゃないんだけど……まぁ、そういうことにしておこうかな」
「気に入らないわね、その言い方。手品じゃないんなら、なんだっていうのよ」
「まぁ、かんたんにいうと、魔法よ」
よりにもよって、とんでもないことを言いだす。この子なりのギャグのつもりなんだろうか。
「ふふふ、魔法って……いまどき、それはないわぁ。小さい子むけのアニメじゃあるまいし」
「アニメって、もしかして“テレビマンガ”のこと?」
「えっ、アニメはアニメでしょ」
どうも、この子とは話がかみあわない。
「そもそも、あなた、だれなの? わたしになにか用でもあるの?」
「わたしは、リリィだよ。大魔法使いのリリィ」
女の子は再び腕を組んで、どこかえらそうな口ぶりで答えた。
「また、ふざけて……だから、そんなのは本当にはいないでしょ」
笑える冗談も、何回もくり返されるとおもしろくない。
「まぁ、いいや。じゃあ、その大魔法使いのリリィちゃんが、わたしになんの用なの? まさか魔法をかけて、ネコにでもするつもり?」
「そんなこたぁ、しません」
リリィと名乗った女の子は、あいかわらずえらそうにいった。
「ミコミコちゃんは、“ミコ・ミコぷろだくしょん”って知ってる?」
また、それか。
「その名前は、さっき園内くんに聞いたけど、残念ながら知らないわね。それはたぶん会社の名前でしょ? 小学生のわたしに聞いて、わかるわけないじゃない」
「ううん、“ミコ・ミコぷろだくしょん”は会社じゃないよ。坂江第二小学校の中にあるんだよ」
「坂江第二小学校?」
坂江小学校なら知っているけれど、坂江第二小学校というのは聞いたことがない。そもそも、そんな名前の学校があったかな。
「よくわかんないけど、とにかく知らないわ。どこかの小学校の中にあるっていうんなら、それこそ区役所にでも電話して聞けばいいじゃない。くだらないことで、人を呼びつけないでよ」
「そんな不機嫌な言い方しなくってもいいでしょ。友だちからミコミコって呼ばれてるっていうから、きっとなにか知ってるだろうと思ったのに」
リリィは、ほっぺをふくらませていった。
「わたし、そういう言い方をする人、苦手なの。なんだかかまれそうで」
「かむわけないでしょ」
そうは言ったものの、確実にロミは不機嫌だった。園内くんがわざわざ呼びにきたからなにかと思ったのに、この展開はないだろうと思う。
「本人はそう思ってるんだろうけどね、聞くほうはそんな気になっちゃうものなのよ……もう、いいわ」
そう言いながらリリィは、スカートの左ポケットから、また小さな粒を取りだした。
「わざわざ呼びつけたおわびよ。ちゃんとキャッチして」
その小さな粒をリリィが指ではじくと、ロミの頭の上より高く飛んだ。それも2つだ。
けれど、やはりミニバスケットボールできたえたロミの動体視力は、ちゃんとそれを目で追って、こともなげに2つともキャッチした。見てみると、うすい紙につつまれたキャラメルだ。
「ちょっと! 食べ物を投げちゃダメでしょ」
そう言いながら顔を前にもどすと––––リリィの姿はどこにも見えなくなっていた。
「あれ? 園内くん、いまの女の子は?」
となりにいた園内くんにたずねると、ふるえた声で答えが返ってくる。
「いや……ぼくもそっちの粒のほうを見てたから」
「そんなバカな」
ロミは公園の中を見まわしたけれど、やっぱりリリィの姿はなかった。いくらせまい公園だといっても、ほんの2秒ほどで人が見えなくなるはずがないのに。
「あの子……まさか消えちゃった?」
「そんなはずないわよ」
ロミは園内くんと顔を見あわせていった。しかし、いくら考えても、あの女の子が見えなくなった理由がわからない。
「いまの子、もしかして」
オバケだったんじゃないの……とロミが言おうとしたとき、園内くんの顔が、クシャッとゆがんだ。まさに泣きだす一歩手前の表情だ。
「うわぁぁぁぁぁぁぁぁぁっ」
次の瞬間、世にもなさけないさけび声をあげて、園内くんは走りだした。そのままロミを置いてけぼりにして、公園を飛びだしていく。
「ちょ、ちょっと待ってよ!」
ロミもあわてて、そのうしろを追いかけた。
(次回更新は8月21日です)