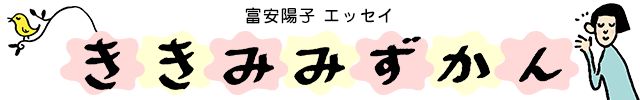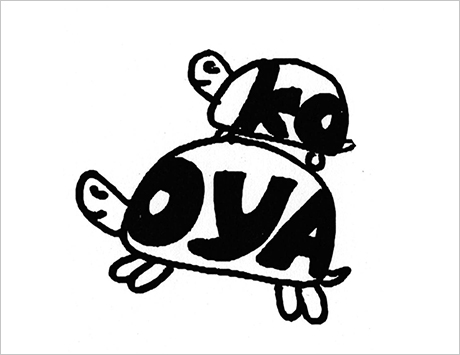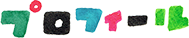オランダ語の《ransel》が語源だそうだ。ランセルとは、軍用の背負式のかばん、つまり背囊のことらしい。ランドセルが訛ってランドセルになり、日本では軍用ではなく、小学生たちの通常カバンとして定着した。
近頃のランドセルは色とりどりで賑やかだ。オレンジやパープル、ピンクや淡いブルーのランドセルをかついでいる子もいる。私たちの子ども時代には、あんなに様々な色のランドセルはなかった。男の子は黒、女の子は赤いランドセルというのが定番だったのだ。色は選べなかったが、それでも、小学校入学を前に、ぴかぴかのランドセルを見た時には胸が弾んだことを覚えている。
私のランドセルは、東京のおばあちゃんからのプレゼントだった。自分宛の荷物が届いて驚いている私の前で、母がにこにこしながらダンボール箱を開けると、中からつやつやとした赤い革のランドセルが出てきて、私は息をのんだ。《富安陽子様》宛の荷物が届くだけでも大事件なのに、中味がおニューのランドセルだなんて!
だなんて!
「ごにゅうがく、おめでとうございます」と達筆なかな文字で書かれた手紙を読み終えるとすぐに、私は新品のランドセルをかついで家中をねり歩いた。
「汚したり、傷がついたりすると困るから、もうしまっておきますよ」
そう母が言わなかったら、一日中、ランドセルをかついでいたかもしれない。ご飯の時も、トイレに行く時も––––。それぐらい、チョー嬉しかったのだ。
ランドセルに名前を書いてくれたのは父だった。我家では何故か私も弟たちも、持ち物に名前を書いてもらう時は父に頼むことになっていた。
まだ少し寒い三月の日曜日の朝、父は八畳の居間の円卓に、まっ赤なランドセルをのせ、その正面にどっしりとあぐらをかいていた。手には、太い油性マジックを握って……。
「みんな、同じランドセルなんだから、名前は大きく書いておかないとな。他の子のと間違えないように」
父はそう言ったのだ。だから、油性マジックで、でっかく、ランドセルのベロンとしたフタの裏側に名前を書くことになった。
私は父の右側にかしこまって正座していた。母は父の向かいに座って、父が字を書きやすいように、円卓の上に伸べられたランドセルのフタを押さえていたように思う。
少し緊張したような面持ちで深呼吸を一つすると、父がマジックのフタを取った。ひやりとした早春の朝の空気の中に、油性マジックの匂いが漂い出た。
息を詰めて見守る私の横で、父は五センチ角はあろうかという大きな字で、太々と名前を書き始めた。
富……安……
「あ……」と、私は声をあげた。
「ああっ!」と母が叫んだ。
「おおっ!」というような声を父が発した。
ランドセルに記された名は――― 。
富、安、秀、雄……父の名だった。
緊張の余り父は、自分の名前を、でかでかと、私のランドセルに書いてしまったのだ。
私はあんなに狼狽する父を見たことがなかった。だから、子ども心に、何か声をかけなければ、と思った。
「お父さん。大丈夫だよ。なおせばいいから」
私がそう言うと父は、
「そうだな、そうだな」と二回うなずいて、《秀雄》の文字を二重線で消した。そして、その横に《陽子》という名を書き入れたのである。その後母が、ベンジンを用いたり、ケシゴムや、果ては紙やすりまで持ち出して奮闘したが、父の失敗を消し去ることはできなかった。おかげで私は六年間、富安秀雄、改め、富安陽子と書かれたランドセルで小学校に通うことになった。もちろん、他の子のランドセルと間違われたことは一度もない。
その思い出のランドセルは、なんとなく捨てるのがもったいなくて、実家のもの置きの中に永い間しまいこまれていたように思うが、いつの間にかなくなってしまった。
米寿になった父に、この話をすると、
「そんなことあったかなあ」と大笑いした後、
「本当に申しわけなかったねえ」と私にあやまった。
今年も新入学の春が来た。色とりどりのランドセルがゆれる町を眺めながら、こんなことを父と二人、思い出している。