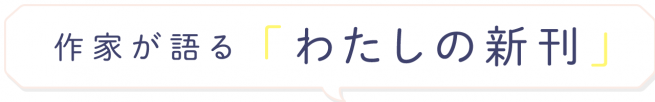『あの花火は消えない』で産経児童出版文化賞フジテレビ賞を受賞した、森島いずみさんの最新作『ずっと見つめていた』。
妹つぐみの化学物質過敏症のため、田舎へ移住を決めた家族ですが、つぐみの兄・越(えつ)は突然の環境の変化に、とまどいを隠せません。両親も、思い描いていた田舎での生活とは異なる現実に直面し……著者の実体験をもとに書かれた、ある一家の再生の物語。
スランプに陥って、生まれた物語
––––都会から田舎へ越すにあたり、独立、開業、自然に根づいた生活を思い描く家族。田舎ならではの自然豊かな暮らしが描かれる一方、その地域に受け入れてもらうという点で、現実的な厳しさもあるストーリーでした。この作品を書こうと思ったきっかけはなんですか。
私は東日本大震災による原発事故のため、福島県から山梨県へ移住しました。何もかも突然のことで、迷いながら結局は移住を決めたわけですが、精神力がついていかず、体調をくずしていました。執筆がうまくいかず、スランプに陥って悶々としていたのです。そこで自分なりに考え、まず原点にもどって、知っていることを書こうと思ったのです。今住んでいる南アルプス市を舞台にした物語なら、遠くへ取材に行く必要もないし、生き生きとした自然描写や空気感を表現できるのではないかと。
私は自然界を文章のなかでできるだけリアルに描写することをとても大切なことだと考えています。読者の五感を刺激するように書きたいのです。そのためには、日々の生活の中で実際に自分が経験し、体感していることを表現するのが近道だと考えました。
––––家族が移住を決意する直接の要因となった、妹・つぐみの「化学物質過敏症」は、香料つきの柔軟剤の増加などで、近年問題になっている現代病ですね。物語のなかでとりあげられたのは、なぜでしょう。
北海道に、自然から採取した色でクレヨンを作っている方がいらっしゃいます。クレヨン工房トナカイの伊藤朋子さんです。伊藤さんは、化学物質過敏症のために市販のクレヨンを使えない子と出会ったのがきっかけで、草花をはじめ、自然の材料だけでクレヨンや絵の具を、10年かけて作り上げました。わたしは、そのクレヨンと出会い、実際化学物質過敏症のために山村留学している子がいることを知りました。
ベトナムの戦争博物館を訪れ、枯葉剤のために多数の悲劇が生まれた現実を目の当たりにしたことや、原発事故で飛散した放射性物質の人体への影響など、自分が学んだことをいろいろ考えました。枯葉剤に使われた物質が、いまだにホームセンターで売られている除草剤に含まれていることを知ったときには恐怖すら感じました。
ひと口に化学物質過敏症といっても、いわゆるハウスシック症候群という建築資材に使われる化学物質によって起きるものから、近頃は洗剤や柔軟剤に入っている香料、そして食品に使われる農薬や添加物に至るまで、実に様々な化学物質によって苦しんでいる人が年々増えています。症状も頭痛や吐き気、ぜんそく、皮膚炎など様々です。そして、治療によって治すことは大変難しいのです。それほどまでに私たちは多種多様な化学物質の中で日々生活しています。
この現実をどう受けとめ、私たちはこれからどうすべきか、今、考え直すときが来ているのではないでしょうか。
そんな問題意識が、この物語を書く動機にもなりました。
今の社会や学校で起きている問題の根本原因は、大人にあるのでは?
––––自分の意志によらない環境の変化は、子どもたちに度々訪れるものです。その変化への向き合い方もわからない曖昧な気持ちが丁寧に描かれていて、共感する読者も多いのではないでしょうか。
子どもは、自分で親や環境を選んで生まれてくることができません。ましてや、今の社会や学校で起きている様々な問題は、多くの場合大人たちが根本的な原因であって、のびのびと育つことのできない子どもたちは、いってみれば愛情やモラルの足りない大人たちの犠牲になっているようにも思えます。
主人公の越くんにとっても、都会から山村へ移り住み、小さな学校に通うことになったのは、本意ではなく、当然困惑も大きかったはずで、できればそのような彼の心の動きも書いた方が、リアリティのある作品になると思いました。
––––作品に出てくるエピソードのなかには、実際にあったことも多いと思いますが、とくに印象にのこっていることはなんですか。
良いエピソードも悪いエピソードも、実際に経験したところと想像で書いたところがあります。
食べきれないほどのタケノコをいただいて、何度も大鍋で煮て塩漬けにしたのは実際の経験から書きましたし、地域の習慣になじめなくてこまったこともありました。
春の山菜採りは子どものころから祖父と山に入っていたのでもともと知識もあり、今でも春になると時間があれば山に行きます。震災による避難生活は経済的に安定したものではなかったので、よく山に入って自然の恵みを食材に利用しました。
ワラビやタラの芽を採りにいくのも今では春の楽しみなのですが、お話の中に登場させるメニューを考えるのも楽しかったです。娘にイラストを起こしてもらったり、実際魚を煮てみたり山菜の天ぷらを揚げたりしながら決めていきました。
 ––––タイトルに込められた思いをお聞かせください。
––––タイトルに込められた思いをお聞かせください。
これはやはり、ラストシーンにこめた思いから出てきたタイトルです。
わたしは構成をしっかり決めてから書くタイプではなく、冒頭のシーンを思いついたら、頭の中で主人公が動いていく姿をうしろからついていくような感じで描写するか、またはラストシーンが見えたら、そこに向かって書いていく方法をとってきました。今回の作品は後者でした。ラストシーンが決まっていたので、そこに到達するために書いていったのです。
ラストシーンはこうしようと、ずっと思い描いていたのがタイトルの決定につながったと思います。
生きづらさをかかえている子どもたちこそ、ほかの人の心の痛みがわかってあげられます
––––産経児童出版文化賞フジテレビ賞を受賞した『あの花火は消えない』、SAPIXの課題図書となった『まっすぐな地平線』。どちらの作品も、どこか生きにくさを感じている主人公が、あたらしい環境や他者との出会いで自分を見つめ直すというストーリーで、今回の作品とも共通項があると思います。物語を紡ぐにあたって大切にされていることはありますか。
今の子どもたちは大変だなあ、と思います。
私の子ども時代は今にくらべると学校も家庭も、ずいぶんおおらかだったように感じています。社会が変化していくのは当然のこととしても、学校も家庭も子どもたちにとってはだんだん窮屈になってきていると感じます。そんな中で、子どもが人間として成長していくためには、いろんな人に出会ったり、トラブルを乗り越えたり、自然の大切さに気づいたりしながら、自分自身も変わっていかなければなりません。
特になにか生きづらさを持っている子は、人間関係に悩んだり、うまくいかないことが多いので、自分の殻に閉じこもってしまう傾向にあると思います。ではその殻を破って自分を開放するために、なにが必要かと考えてきた結果、『あの花火は消えない』という作品が生まれました。『ずっと見つめていた』は、そのほかに環境問題に対する考えも盛りこんだつもりです。人間ってやっぱり、大きな自然に生かされているものだと思います。私たちが自然環境を破壊してきた結果、化学物質過敏症などという病気まで生まれてしまったわけですから。
それと、生きづらさをかかえている子どもたちのほうが、ほかの人の心の痛みをわかってあげられる、繊細で純粋な子が多いと思っています。心がきれいで正義感が強く、だからこそ学校生活でも少数派でよけいに生きづらいんです。そんな子どもたちがもっと生きやすい社会にするには、大人たちももっと考え深く、理解する努力をして、変わっていかなければなりません。そのことに、ひとりでも多くの人に気づいてほしい。
わたしがつづるストーリーはいつもそんな希望から生まれてきます。
––––最後に、読者へメッセージをお願いします。
この作品を読んで、もし心に残ったことがあったら、どうしてそのことが心に残ったのか、ゆっくり時間をかけて考えてみてほしいなあ、と思います。
この物語にこめたメッセージを受け取っていただけたらうれしいです。
––––ありがとうございました!

森島いずみ
秋田県に生まれる。立命館大学文学部卒業。通訳業のかたわら児童文学を書きはじめ、「ニイハオ! ミンミン」で第15回小川未明文学賞優秀賞、『パンプキン・ロード』で第20回小川未明文学賞大賞受賞。原発事故があった福島県から、山梨県に移住し、現在に至る。