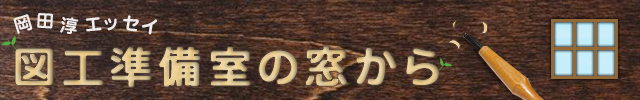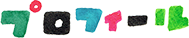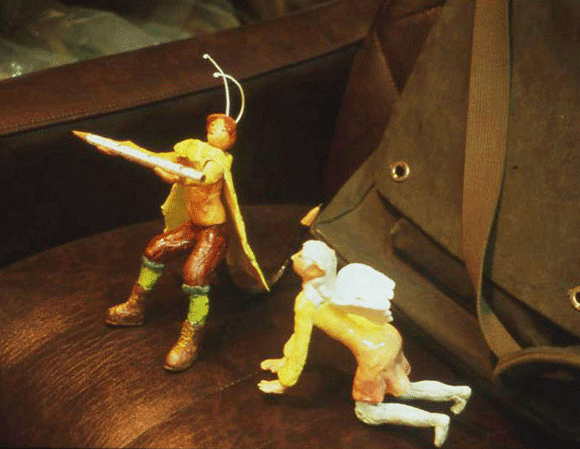
右が「しりたがりやの精」、左の鉛筆をさしだしているのが「さっさとしごとをせい」。
図工のジャンルのひとつに、お話の絵、というのがある。先生が読み聞かせたお話を、絵にするのである。
図工の先生になって六年めに、二年生を担任しているタジマ先生に、お話の絵について相談された。いい題材になるお話がないだろうか、と。
ぼくは自分のことを謙虚な人間だと思っていたふしがあるが、このときのこたえかたや最初の図工展のことを考えると、はた迷惑な理屈っぽい理想主義者だと知れるのである。
こういうこたえかたをした。
既に絵本などでその話の絵を見たという場合、その影響は避け難い。見たことも聞いたこともないという話がベストである。つまり、絵になる場面を多く含む話を、つくって話してやればいい––––。
話なんて簡単にはつくれない、とタジマ先生はいい、つくってつくれんこともなかろうと言ったのはぼくである。「そしたら、淳さん、つくってくれるか?」タジマ先生は、麻雀の名手である。場の空気を読み、相手の手の内を読む。
「……つくってみよか」 ロン。
一週間ほどで、花を食べる怪獣ムンジャクンジュの話を作った。絵になる場面満載である。
話ができた、とタジマ先生に言うと、「来週の金曜日、わたしは研究会に出張せんならんねん。淳さん、金曜日の三、四時間目あいてるやろ。せっかく話を考えてくれてんから、ついでに授業もしてくれへんか?」タジマ先生は、卓球の名手でもある。相手のバックをせめておいて、フォアへ打ち込む。
「……そしたら、するわ」 ツー、ゼロ。
その怪獣の話、自分でもおもしろいなあと思ったぼくは、新たに構想を練り直し、原稿用紙に書き始めたのである。挫折と復活を繰り返し、四百字詰めで三百枚の物語を書き上げた。三年半かかった。ただ書き上げたくて書いたのだが、ひとが読めばどう思うだろうと、近所の児童書専門の本屋さん〈ひつじ書房〉に持っていった。〈ひつじ書房〉の店主、平松二三代さんは児童書にずっと関わってこられた方だから、意見のひとつも聞かせてもらえるかも、と思ったのだ。
すると平松さんはていねいに読んで下さり、紹介状に作品の概略まで添えて、偕成社に送って下さったのである。
ある日、東京の偕成社から、編集部の相原法則さんが神戸のぼくの部屋にやってきて、東京弁でこうおっしゃった。「あのムンジャクンジュ、おもしろいですから」
ここまで聞いてぼくは、本になるのだ! と思った。が、相原さんはこう続けた。「書き直しなさい」
これは二百枚でかける話だ、とおっしゃっるのである。相原さんの指導助言で、半年かけて書き直し、本になった。 ぼくはそういういろんなひとのおかげで物語をつくるひとになれたのだが、その重要なきっかけをつくってくれたタジマ先生は、巧まずして幸運を授けてくれた、ぼくの、いわば、そのつもりのなかった、天然の守護天使なのである。