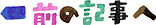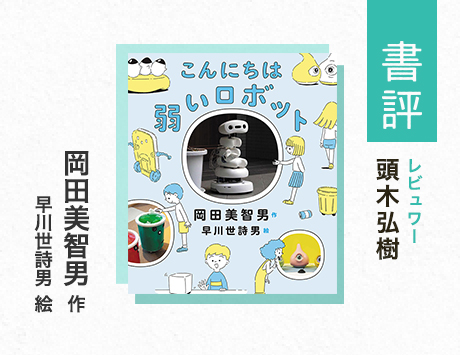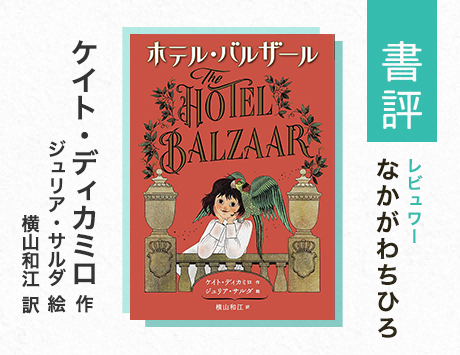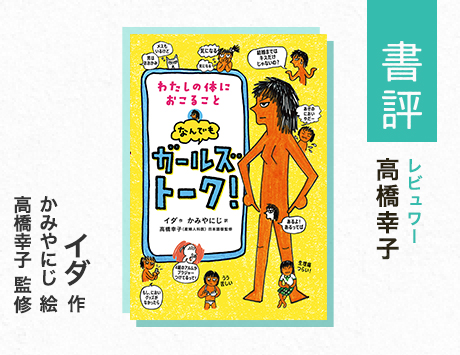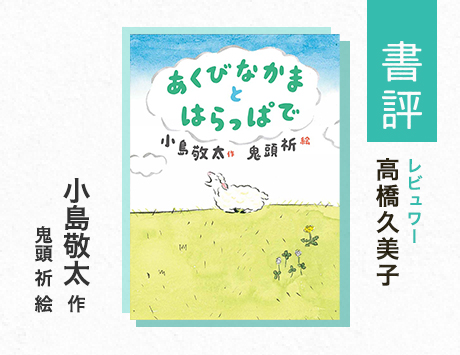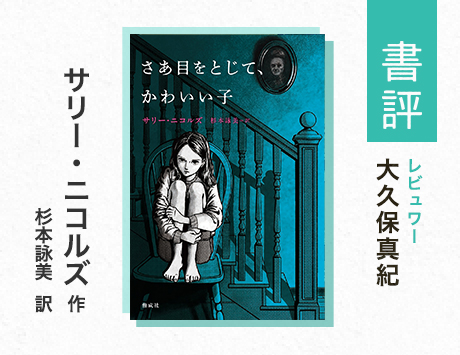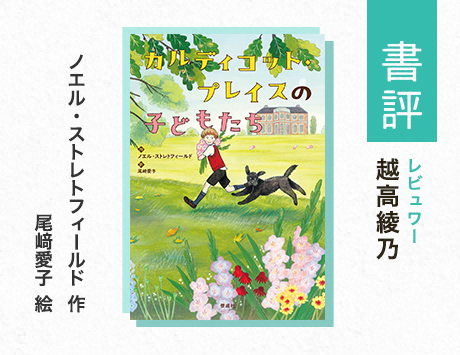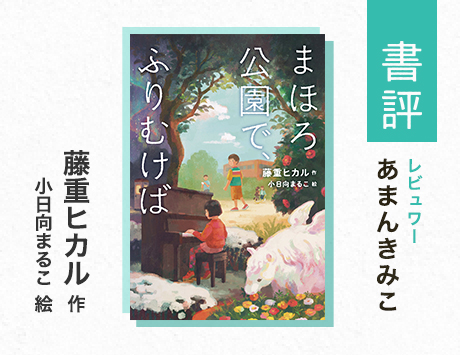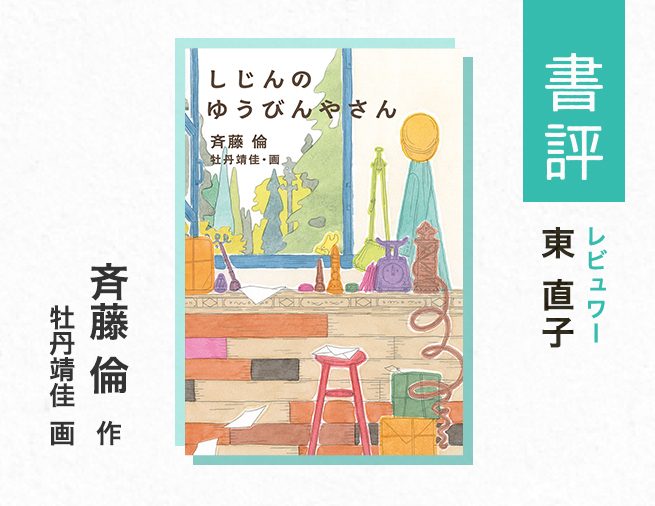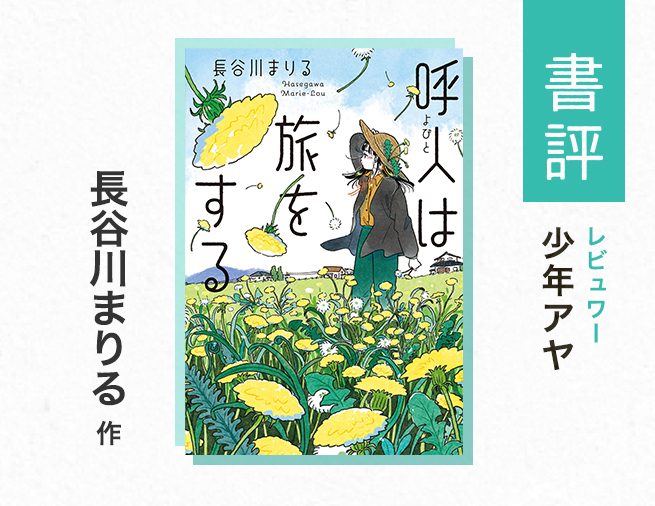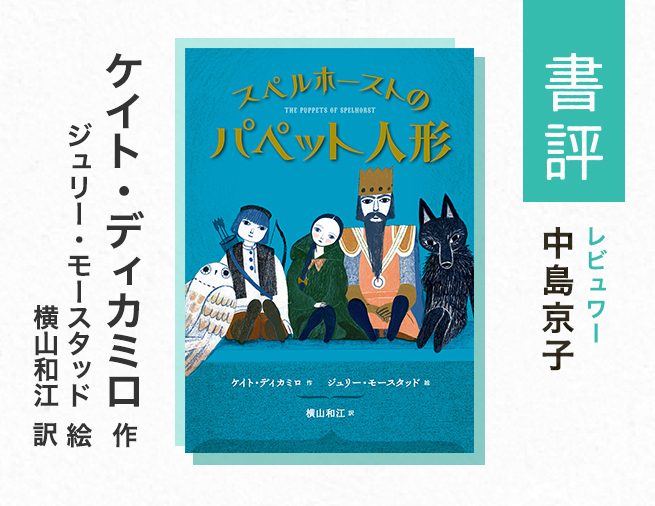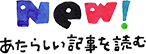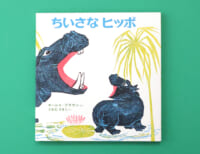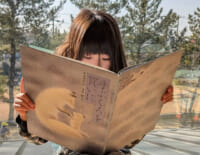脳性まひのために、車いすで生活をしている主人公エリーは12歳。家ではママに、学校ではエリー専用の補助職員に、あれこれと世話を焼かれる日々を過ごしている。エリーの楽しみは家のキッチンでのお菓子作りだ。
ある日、エリーは学校のランチタイムに外に抜け出して、ゴミ箱のそばのひだまりでひとりお弁当を食べる。ひだまりの気もちの良さについうとうとしたエリーは授業に遅れ、そのことで大騒ぎになる。騒いでいるのはクラスメイトではなく、補助職員そのひとだ。それというのも、とエリーは冷静に考える。
「わたしには健康上のリスクがあるからだ。(中略)でも、なにもかもにウンザリするときもあるんだ。ほかのみんながふつうだってことを、目撃しつづけるのがいやになるときが。」
できることまでできないと見なされては苛立ち、できないことを思い知らされれば傷つく。外側と内側からの「ふつうじゃない」という声を蹴とばすように、エリーは生きている。エリーの内面の清々しさにたちまち魅了されてしまった。
ところが、エリーには友だちと呼べる友だちがいない。それはおそらく、エリーがその魅力を内側に留めたままにしているからだろう。だれにでも見える車いすとちがって、こころは簡単には見えないから。
そんなエリーの毎日に変化が訪れる。認知症のおじいちゃんと暮らすおばあちゃんの負担を減らそうと、ママが引っ越しを決意するのだ。
あたらしい学校で、歩けない子としてまた一からやり直すなんてと、さすがのエリーも怖気づくのだが、ママの決意が変わらない以上、ついていくしかない。
いまはもう「ふつう」とは言えなくなってしまったおじいちゃん。
そのおじいちゃんとおばあちゃんの暮らすトレーラーハウスは、「ふつう」の家を持てないひとたちの住まいとされている。
引っ越し早々、エリーは近所に住むコラリーという少女に出会うのだが、自己紹介のあと、コラリーは言う。「いい車いすだね」って。まるで、「いいメガネだね。似合ってるよ」って言うみたいに。
フラットでいい子とわたしはすぐに思ってしまうのだけど、ものごとはそんなに単純じゃない。コラリーもまた、トレーラーパーク住まいの自分とふつうの家に住む町の子とを分けて考えているし、それは町の子側も同じだ。
コラリーは、どこにだって線引きがあると言う。「鉄道の線路とか、道路とか、橋とか、なんでもいいんだ。そういうものが、変なのものとふつうのものを仕分ける。」と。
「だけど、うちのママは先生だし、バートのパパはフード・カンパニーを経営しているじゃない」というエリーの反論は力なく聞こえる。なぜなら、その線引きこそ、エリー自身が身を持って感じ続けてきたことなのだから。
ところで、このバートもコラリーと同じトレーラーハウスの住人で同級生。頭はいいが、ちょっと変わった子で、バートをよく知るようになる前は友だちなどなれないと思っていたくらいだ。
ここにもやはりコラリーの言うところの線引きがある。「変なもの」と「ふつうのもの」との線引き。それはわたしたちのまわりにもいくつも存在している。
さて、ここからが本書の素晴らしいところだ。彼らがどうやって友だちになっていったか、トレーラーパークの子と町の子の線は乗り越えられることなく終わるのか。そしてエリーが波にうかぶというタイトルの意味は?
それらは読んで、エリーたちの行動のひとつひとつを知って感じてほしい。わくわくすることまちがいなしだ。そしてそのあとにこころに生まれるひとつの問いは「ふつう」ってなに? ということ。