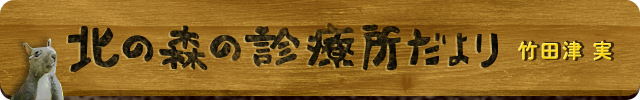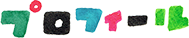12月。夏の名残の湿気が北からの冷気で一気に地上に降りそそぐ。六角形のその結晶はどれひとつとっても同じ形のものはないという。そのときの気分としか言いようのないような、大気の微妙な息づかいによって形をそれぞれ変えて降りてくる。一片の重さ0.1ミリグラム、面積1平方メートルに1センチの深さに積もるためには、約500万個の雪片が必要だと学者が算出した。それを知ってからは、雪が降ると外に飛び出し、ただただ「なるほど」といいながら天をあおいでそれを感じようとしている。
「色の白いは七難を隠す」ということわざもあるが、何も隠さず逆に大地はおしゃべりになると私は思っている。夜半、玄関で居候的入院をしている患者の例外的に名をもらったアカゲラ・ゲラッピーがキョッキョッと警戒の声をあげるのを聞いたような気がする。彼は右眼が見えない。次の朝、玄関わきの車庫をのぞくと足跡。

夜半、玄関番のゲラッピーを起こした犯人を知る。エゾクロテンである。夏から秋、我が家と勝手に決めたエドヤチネズミの家族を狩ったらしい。吹き込んだ雪がドラマの跡を物語る。ついでにいつもの散歩のコースをひとまわりする。アカネズミやエゾヤチネズミの前夜の散歩道を知る。エゾリスのきまぐれ、狩りに成功した足跡を見る。証拠に両足の間に赤い血が残る。春先まで治療のために給餌していた台のまわりにエゾタヌキの足跡。その数から2頭だと知る。クロテンの足跡が裏山に続いていたのであとを追ってみる。ドイツトウヒの森の中で食事の跡を見た。3週間前、近くのお百姓さんが農作物を荒らすといって撃った若いエゾシカの一部があった。森中の生きものがご相伴になっているらしい。ブラインドを張って夕方観察することにした。太陽が西の山にかくれて30分。やはりクロテンがやってきた。

次の日、また足跡を追ったら、クロテンは少し大回りして、我が家の車庫のタイヤを積んだ奥へ。そこをねぐらにしているようだ。雪の上の足跡をたどると自然は物語に満ちた舞台だと知る。
一面の銀一色は、そこに登場する役者の衣装を際だたせる。ヤマガラの栗色に思わず立ち止まる。ひっそりとたたずむ1羽のカラスの姿にみとれてしまう。ありふれたズミの木にやってきた1羽のツグミも、舞う雪に新種の鳥を発見したような気分にさせられる。

北海道大学にいた故中谷宇吉郎先生は「雪は天から送られた手紙である」といったが、雪は北の大地の演出家であると思ってしまう。
オコジョの足跡を見た次の日、ベランダの下から散歩に出る私を見送る白毛となった当人をみる。