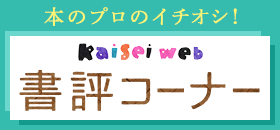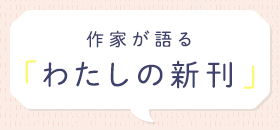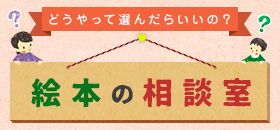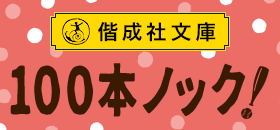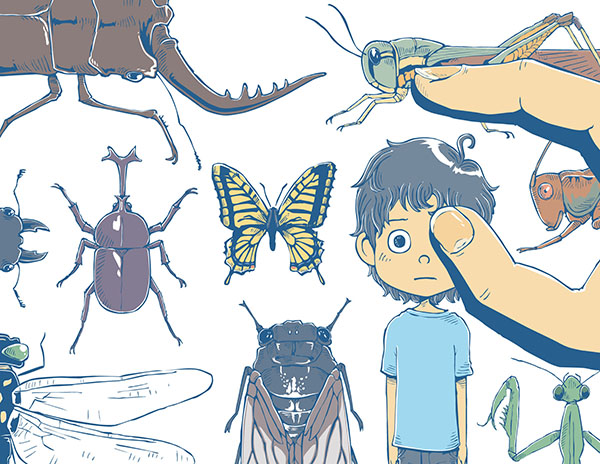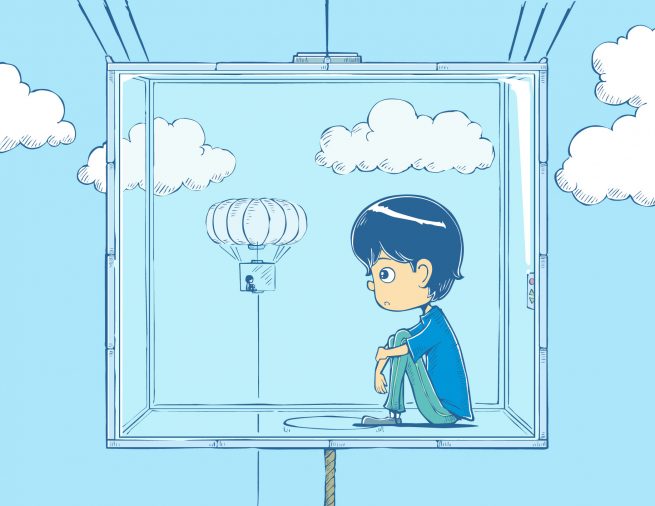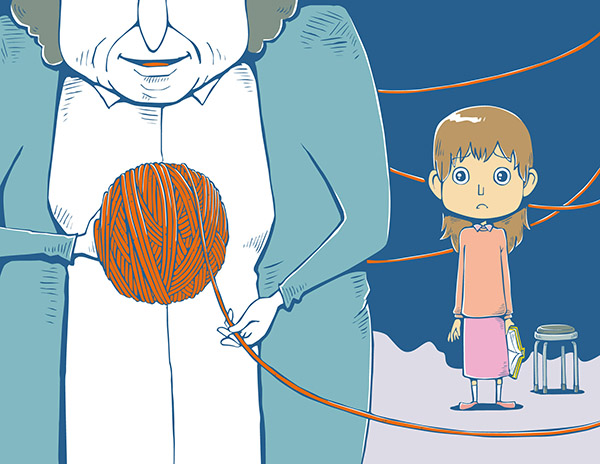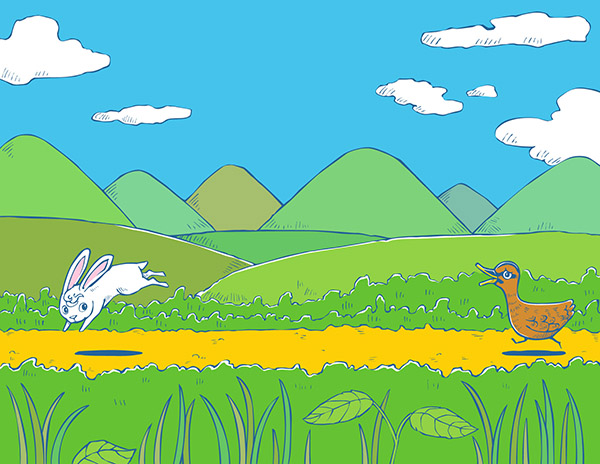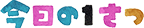夏の夜なのに、妙(みょう)に冷たい。
特に、足もと。一歩、ふみ出すごとに、見えない霧(きり)が、足もとにまとわりついてくるような気がする。冷気というやつだ。
ゾクゾクする冷たい気配が、足から、背中へとはいあがってくる。首筋まで、ぶるぶるとふるえてしまう。――いや、この感触(かんしょく)は、けっして、気のせいではない……と思う。
――いやだなあ……。
ぼくは、目の前にひろがる闇(やみ)に、身をすくめた。
こんなところに、たった一人で足をふみ入れるなんて。本当に、かんべんしてほしい……。
でも、この闇の奥(おく)の目的地まで行って帰ってくるというのは、〈博士〉と交わした約束。ぼくにあたえられた、だいじなミッションなのだ。
「あなただけがたよりなのよ」
〈博士〉は、ぼくを一人前の男と見こんで、こう言ったのだ。「この実験が成功するかしないかは、すべて、あなたの勇気にかかっているの」
そう言って、〈博士〉は、ぼくに、特別な装置をつけてくれたのだ。
――それでも、こわいものは、こわいよ……。
なんとか、勇気をふりしぼり、冷気をふりはらうようにして、ぬかるんだような土の上に、一歩だけ、ふみだした足が、なにか冷たい指のようなものに、つかまれたような気がした。
「うわッ」
と、声を出して、足を見た。
それは……足にからみついていたそれは……こわいものではなかった。
それは、花だった。見たこともないような青い花だ。さいしょの一瞬(いっしゅん)だけ、五本の指をのばした人の手首にも見えたけれど――五枚の花びらをひらいた、大きな花が、つまさきに、ひっかかっていただけだった。
「おどかすなよ……でも、ずいぶんと、きれいな花なんだな」
これまで、道ばたの花なんかに見とれたことなんてなかった。あんまりにもこわかったものだから、花だと思ってほっとしたとたんに、その色や形の美しさが、ジーンと心にしみてきたんだろう。だけど、まだ、ほっとしている場合じゃない。
〈博士〉との約束は、まだまだ、この先へ行くことだった。
この場所は、むかしは、ちゃんとしたお寺の境内だったという。いまは、お堂らしき建物もあちこちでくずれ果て、廃墟(はいきょ)みたいになっている。
そう。まるで、なにかが、あらわれてもおかしくないような……。
そうなのだ。……ここは、そのテのウワサでは、かなり有名な名所。――そう。アレが「よく出る」スポットなのだ。いままでアレを見たことがないって人でも、ここに来れば、必ずアレを見てしまうという、おそろしいスポット……。
え? アレって、なにかって? アレというのは、その……アレだ。さすがに、口に出して言うのは、こわい……。こわすぎる……。
だから、ぼくがこわがらなくてすむようにと、〈博士〉は、この装置をつけてくれたんだ。
「だいじょうぶ。これはあなたのための特別な装置だから」
〈博士〉は、そう言いながら、ぼくの頭に、なにやら、不思議なものをかぶせた。ふといツル草を編んでつくったような、ベルトとも、ヘルメットともつかない、かぶりものだ。
「なに、この帽子(ぼうし)みたいなの? お守り?」
「お守りよりも、効き目があると思うわ。こわがりやさんのあなたにとってはね」
こわくなんかないや……と、強がりも言えなかった。〈博士〉の指定したゴールは、この廃墟の奥だからだ。
――すべては、ぼくの勇気にかかっているんだからな。

ぼくは、ぬかるんだ道を歩きつづけると、大きな門柱のようなものが見えてきた。前は、お寺のりっぱな山門だったかもしれないけれど、ぼろぼろの木の柱だ。こんなところをくぐるのいやだな、と思いながら、見あげると、大きな提灯(ちょうちん)がかかっている。古くて、やぶれかかった提灯だ。
いやだな、いやだな、と思いながら、そばを通りぬけようとすると、提灯に、ぼんやりと、光がともった。あれっと思った、次の瞬間(しゅんかん)、提灯は、がばっと口を開いて、なかから、にょろりと長い舌が……。
「うわッ」
と、さけんで、ひっくりかえりそうになった。でも……よく見ると、やぶれた提灯の内側から、たれさがっているものは……赤い花だ。大きな花びらの表面が、どこか、ヌルヌル、ヌラヌラと、光って見えるけれども、これまた、見たこともないような、めずらしい花じゃないか。
「ここは、ひょっとして……」
〈博士〉が「幽霊(ゆうれい)の 正体みたり 枯(か)れ尾花(おばな)」ってコトワザを言ってたことを思いだした。こわがって、幽霊だと思ってたものが枯れた花だったという意味だ。だとすると……。
ぼくは、立ちあがって、まわりを見まわした。 これまで、こわいオバケが出るスポットだというウワサを信じこんでいたけれど、本当は、ちがうんじゃないの?
めずらしい植物や、美しい花ばかりを集めた植物園。それこそ、秘密の花園だったりして?
その証拠(しょうこ)に……。
奥にむかって、足をふみ入れると、あちこちに、いろんな、めずらしい花が見えてきた。
髪(かみ)の長い女の人みたいに、長くて細い枝を風になびかせて、おいでおいでしているように見えるのは、紫(むらさき)のしだれ桜なのだろう。
古井戸のあたりにからみついているものは、ちょっと見にはガイコツみたいに見えるけれど、あれは、キクの花――人の頭ぐらいの大きさの白いキクの花なんだろうか。
遠くから見ると、あでやかな晴れ着を着て、顔半分を赤く血にそめた女の人みたいに見えるものも、いろんな色の花が密集して、そう見えるんだろう。
どれもこれも、とってもきれいだ。
クモみたいに地面をはいつくばっているように見える花も、ヘビのように長い首を伸ばしているように見える花も通りこして、約束通りの目的地――廃墟の奥に行くと、そこには、くずれた本堂があって、空飛ぶ火の玉みたいに、きれいな花が群れをなして、飛びだしてきた……。
そんなこんなで。
「〈博士〉。ぼく、ミッションをクリアしたよ!」
ぼくは、すっかりうれしくなって、笑いながら、もどってきた。「すっごく、きれいだった!」
門の外で待っていた〈博士〉は、うなずきながら、
「そのようすなら、実験は大成功ね」
〈博士〉は、得意そうに、「お化けがこわくなくなったでしょ。そのクサカンムリをかぶっていたから」
ぼくの頭の上を、ゆびさした。
「クサカンムリって?」
「お化けの『化』っていう字に、〈クサカンムリ〉をつけると『花』になるわよね」
「え? え? まさか!」
〈博士〉は、笑いながら、「もちろん、恐怖心(きょうふしん)の転換(てんかん)には、カガク的な理由もあるわ。その頭にかぶる装置から出るカガク物質のはたらき。脳波のデータも採取できたし」
〈博士〉は、満足そうに言った。「人体実験は大成功だわ」
頭の装置に手をのばす〈博士〉の顔が、その瞬間、牙(きば)を生やしたバラの花に見えた。
「あ、〈博士〉もお花に見える。〈博士〉も、お化けだったの?」
「お化けのわけないじゃない」
花がにやりとわらった。「あたしは、化学者だもん」
井上雅彦
1960年東京生まれ。星新一ショートショートコンテスト’83で作家デビュー。ちょっと不思議で怖い物語が得意。短編集『四角い魔術師』(出版芸術社)、長編『夜の欧羅巴(ヨーロッパ)』(講談社)などがある。99年に日本SF大賞特別賞を受賞。
イラスト:アカツキウォーカー